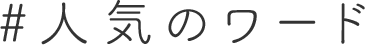特集コラム
給食業務に携わる管理栄養士・栄養士さん必見!日本人の食事摂取基準(2025年版)総論を解説
総論を解説.jpg)
令和6年10月に厚生労働省から「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書が公開されました。本コラムでは、こちらの総論において給食業務に携わる管理栄養士・栄養士の方に押さえておいてほしい主な変更点について解説します。
今回の改定の趣旨と基本構成の変更
今回の改訂では、健康日本21(第三次)の方針を踏まえた内容に変更されました。食事摂取基準の基本構成では各論の第3節のタイトルが、2020年版では「生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連」だったことに対し、2025年版では「生活習慣病及び生活維持・向上に係る疾患等とエネルギー・栄養素との関連」となっています。
また、新たに生活機能の維持・向上に係る疾患として「骨粗鬆症」が追加され、骨粗鬆症に関連するエネルギーや栄養素についてもまとめられています。
さらに、第3節の頭に目的や活用上の留意点が新たに追加されました。留意点としては、エネルギー・栄養素の摂取量を策定することが目的ではなく、生活習慣病等とエネルギー・栄養素との関連や正しい理解を促すことを目的としていると記載されています。治療等では、それぞれの疾病の診療ガイドラインを確認することが必要です。この節では肥満や肥満症、やせの項目は設けられていませんが、多くの生活習慣病等と密接に関連している点については理解しておきましょう。
策定方針について
今回の改訂において、対象とする集団の範囲は健康なものを中心に構成されている集団としており、2020年版と変わりません。
策定する項目については「アルコール」に関する部分が変更されました。今までアルコールに関する項目は炭水化物の章に含まれていましたが、エネルギー産生栄養素バランスの章に移動しています。アルコールは化学的にも栄養学的にも炭水化物と異なること、また栄養素ではないことが明記されています。
また、健康への影響などについては、エネルギー・栄養素との関連の章や厚生労働省が作成した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を参照するよう記載されているので、チェックしておくとよいでしょう。
策定の基本的事項について
2025年版では、推定平均必要量について一部の内容が追加されています。推定平均必要量の目的が摂取不足の回避であること、またその「不足」の定義が栄養素によって異なるという点は以前と変わりません。今回の改訂では、栄養素の摂取量や生体内での当該栄養素の機能などを示す生体指標が複数使用可能となっている最近の背景から、それに基づいた推定平均必要量の見直しが行われました。それぞれの栄養素で用いられた推定平均必要量の定義は、各論で確認しておきましょう。
また、レビューの方法では、目標量のエビデンスレベルが表でまとめられています。今回の改訂では、たんぱく質のエビデンスレベルがD1からD2へ下がりました。理由としては、関連する研究が複数報告されているものの、摂取した栄養素の「量」を評価した研究が非常に限られているためと記載されており、今後の課題としています。
参照体位については、18歳以上成人の区分が追加され、男女合わせた参照身長及び参照体重が明記されました。
食品成分表の利用と今後の課題
現在、国内で使われている公的な食品成分表は日本食品標準成分表2020年版(八訂)ですが、2025年版の食事摂取基準では、一つ前の食品成分表である日本食品標準成分表2015年版(七訂)に基づいて計算されたエネルギー・栄養素摂取量に対応するものとして策定されています。理由としては、2025年版の食事摂取基準を策定するにあたって入手可能な研究結果が、主に七訂の方法で計算されたエネルギー・エネルギー産生栄養素の量を使っているからです。
食品成分表は、七訂から八訂になった際に、エネルギー量の計算や食物繊維の測定法が変更されたため、食品中の成分値に変化がありました。これにより、日本人の食事摂取基準(2025年版)で示された基準値と、日本食品標準成分表(八訂)を使って栄養価計算を行った結果を比較すると、測定方法の違いによる誤差が発生することがあります。今後の課題として、七訂と最新版の食品成分表を使った場合に生じる栄養価計算結果の差について検討が必要だと記載されています。今後の議論に注目です。
まとめ
日本人の食事摂取基準(2025年版)では「健康日本21(第三次)」の方針が反映されました。一部の内容が変更となっていますが、活用の基本的な考え方は2020年版と同様です。集団の食事改善を目的とする場合は、その目的に応じた指標から食事評価を行い、食事改善の計画と実施を行うこととしています。その際には食品成分表との関連をきちんと理解することが必要です。
また、各論を理解し、活用するためには、総論を十分に理解することが必要不可欠です。2020年版からの変更点を抑えながら理解を深めましょう。
参考文献
・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html(閲覧日:2025年6月2日)
・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html(閲覧日:2025年6月2日)
・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_539644.html(閲覧日:2025年6月2日)
・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)スライド集について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49171.html(閲覧日:2025年6月2日)